こんにちは、つかなむです
今回は「タイとスラー」について、リズムの観点と演奏の観点からお話しします。
見た目がよく似ている「タイ」と「スラー」ですが、意味や演奏上の役割はまったく違います。しっかり区別して理解することで、リズムの安定や表現力の向上につながります。
タイとスラーの違い
| 項目 | タイ | スラー |
|---|---|---|
| 意味 | 同じ音をつなげて、音価を伸ばす | 異なる音を滑らかにつなげる |
| リズム上の役割 | 拍をまたぐ(シンコペーションなど) | リズム自体は変えない |
| 弓の使い方(チェロ) | 基本的に同じ方向で伸ばす | 同じ弓で複数音を弾く |
リズムの観点から見るタイとスラー
● タイ
- 拍をまたぐリズムを作ることで、リズムに変化とアクセントのずれを生みます。
- 例:♪ + (4分+8分)=拍をまたいで「タ~イ」と音が続く。
- シンコペーションなど、リズムに躍動感を与える場面で多用されます。
● スラー
- リズムは変わらず、音符がなめらかにつながるだけ。
- 強拍と弱拍を滑らかに接続し、より歌うような表現に。
- 演奏者にとっては「どこまで一息で弾くか(フレーズ)」の目印にもなります。
演奏の観点から見るタイとスラー
● タイ
- 同じ音を弓を返さずに伸ばして弾くのが基本。
- ただし、**拍の頭で弓を引き直す(擬似アーティキュレーション)**という手法もあります。これは音の区切りを明確にしたい場合や、指揮者の意図によって選ばれることも。
● スラー
- ひとつの弓の中で複数の音をなめらかに弾きます。
- アクセントをつけず、音と音の間にブランクを作らないよう意識。
- 弓のコントロール(スピード・重さ・場所)が重要になります。
実践のヒント
- タイとスラーが混ざっている楽譜(いわゆる「タイスラー」)では、
- タイ:音を繋げることを忘れずに
- スラー:弓を返さずなめらかに
- 場合によっては拍頭を軽く引き直すことで、リズムの明瞭さを出すことも可能
まとめ
- タイはリズムに影響を与える要素で、拍をまたぐ音価の延長。
- スラーは演奏の滑らかさを表現する記号で、弓の動きをコントロールするための指示。
- タイ+スラーが混在する場合には、演奏者の解釈や状況に応じて「引き直す」などの工夫も必要です。
楽譜をよく観察し、「今は何が書いてあるのか?」を意識するだけでも演奏がぐっと変わります。ぜひ、練習の中で意識してみてくださいね!
それではまた!

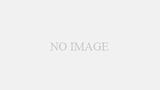
コメント