こんにちは、つかなむです!
今回は、音楽の基本中の基本——p(ピアノ)と f(フォルテ)などの強弱記号についてお話しします。
でも、ちょっと待ってください。「強い」「弱い」と言ってしまうと、どこか体育会系っぽく感じませんか?
実はこの「強弱」、もっと奥深くて、むしろ“表現の対比”や“空間の広がり”を感じるようなものなのです。
強弱記号ってなに?
楽譜に出てくる「p」や「f」などの記号は、「ダイナミクス(音の強さの変化)」を示すものです。主なものはこちら:
-
p(ピアノ) … 静かに
-
f(フォルテ) … 大きく
-
pp(ピアニッシモ) … とても静かに
-
ff(フォルティッシモ) … とても大きく
-
mp(メゾピアノ) … やや静かに
-
mf(メゾフォルテ) … やや大きく
これらは単なる「音量」だけではなく、音楽のキャラクターを決める大切な要素です。
強弱=「強い/弱い」じゃない?
強弱という言葉に引っ張られがちですが、
本質的には「強い音」「弱い音」というよりも、
-
動と静
-
外向きと内向き
-
開と閉
-
表と裏
-
光と影
そんな対比の感覚を持って捉えると、表現がぐっと豊かになります。
たとえば…
-
f(フォルテ)は「前に出る」ようなエネルギーや存在感
-
p(ピアノ)は「引く」力や静けさ、内面の響き
つまり、大きい vs 小さいというより、外向き vs 内向きのイメージなんです。
音量は“相対的なもの”
また、pやfは絶対的な音量ではなく、相対的なものです。
小さなホールと大きなホールでは、同じ「f」でも違って聞こえますし、曲の冒頭と終盤でも印象が変わります。
💡ポイント:
-
「この曲の中でのfって、どんな存在感だろう?」
-
「このpは、前のfと比べてどう違わせたいのか?」
こうした意識が、演奏の深みをぐっと引き出してくれます。
チェロ演奏でのpとfの工夫
チェロは、弓の圧とスピード、弓の位置(駒寄りか指板寄りか)で、強弱のニュアンスを作り分けられる楽器です。
🎻 f(フォルテ)の弾き方
-
弓をしっかり乗せて、スピードを保つ
-
弓の根元〜中間を使うと響きが安定
-
圧だけでなく、「広がるように」弾く意識が大事
🎻 p(ピアノ)の弾き方
-
弓を軽く、少し指板寄りで
-
音がつぶれないように、弓のスピードを保つ
-
「こっそり語る」ような音色で
pからfへ、fからpへ —— “動き”が音楽を作る
pとfは、対比してこそ生きるものです。
曲の中で、クレッシェンドやデクレッシェンドを使って変化させると、物語性がグッと高まります。
音量が変わることで、
-
空気感が変わる
-
聴き手の意識が変わる
-
感情の流れが見えてくる
そんな“ドラマ”が音楽の魅力ですね。
まとめ
-
「pとf」は音の大小ではなく、内と外、静と動の表現
-
強弱は相対的な感覚で捉えると、より自然に表現できる
-
チェロでは弓の使い方で、繊細にニュアンスを描ける
-
強弱の対比が、音楽に奥行きを与える
楽譜の記号、もっと楽しもう!
「pとfをどう表現しよう?」と考えることで、音楽がグッと楽しくなります。
ただ大きい・小さいではなく、“自分の中にある表と裏”を感じながら演奏してみてくださいね。
それでは、また次回の記事で!

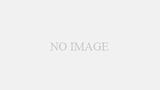
コメント