オーケストラの調弦が「A」で行われる理由:赤ちゃんの泣き声との関係とは?
こんにちは、つかなむです!
今回は、オーケストラで調弦の基準音として使われる「A」の音(440Hz)が、赤ちゃんの泣き声に由来するという興味深いテーマについてお話しします。この説、皆さんも一度は耳にしたことがあるかもしれませんね。
赤ちゃんの泣き声と「A」の音
赤ちゃんの泣き声が「A」の音(440Hz)に近いという話は、一部で支持されています。
特に生後3か月までの赤ちゃんの泣き声は、人間の耳が最も敏感に反応する周波数帯域に位置しており、この音域が親や周囲の大人に「気づきやすい」生物学的な利点をもたらしていると考えられています。
ですが、この説には議論の余地があります。赤ちゃんの泣き声が常に440Hzというわけではなく、泣き声の音域には個体差があるため、一概に「赤ちゃんの泣き声=A音」とは言い切れないのです。
オーケストラの調弦が「A」で行われる理由
一方、オーケストラが「A」の音を基準に調弦を行うのは、楽器の調整がしやすいためです。
特に、基準音を出すことが多いオーボエは、非常に安定した音を出す楽器であり、その音に合わせることでオーケストラ全体の音が調和します。
「赤ちゃんの泣き声がA音である」という説がオーケストラの調弦に影響を与えたという直接的な証拠はありませんが、音楽的基準が統一される過程で、そうした説が付随的に広まった可能性もあります。
他に考えられる説
- 音楽的基準の歴史
現在の国際基準である「A=440Hz」が採用されたのは1939年。それ以前は地域ごとに基準音が異なっていました。この統一の際に赤ちゃんの泣き声が基準に影響を与えたという説もありますが、具体的な証拠は乏しいです。 - 生理的な理由
赤ちゃんの泣き声が440Hz付近である理由として、進化的に親が泣き声に気づきやすくなるためという考え方があります。この音域は周囲の音に埋もれにくく、赤ちゃんの「生存」を助ける適応の一環だという説です。 - 文化的な影響
赤ちゃんの泣き声と「A音」を結びつける考えは、科学的な根拠というより文化的な伝承や迷信に基づく部分もあるかもしれません。このため、一部では「神秘的なエピソード」として語られることもあります。
結論
赤ちゃんの泣き声が「A=440Hz」であるという説には一定の科学的根拠があるものの、オーケストラの調弦が「A」で行われる直接的な理由ではありません。オーケストラが「A」を基準にするのは、楽器の調整のしやすさが主な理由です。赤ちゃんの泣き声と音楽の基準音を結びつける話は、文化的な解釈や生理的な理由から広まった可能性が高いと言えるでしょう。
音楽と生物学、そして文化が交差する興味深いテーマですよね。
これからも音楽の背景にあるさまざまなエピソードを探求していきましょう!
それではまた! 🎵

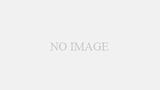
コメント